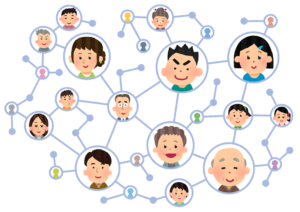「わたし」の集合体の政治なのか、「わたしたち」の政治なのか

平井一臣(2020)『ベ平連とその時代 身ぶりとしての政治』有志舎、を読了。ご恵投いただいた書籍で、すでにお盆休み中には読了だったのだが書評をめぐっていろいろ考えるところがあり、コメントが書きにくくなっていた。
平井一臣先生は当方が長年師事している方で「超えることができない壁」のお一人。先生の手法は、国の政治などを語る際に中央の姿のみをフォーカスするのではなく、中央−地方で起こる運動により政治(的なもの)が互いに影響を及ぼしながら、再形成されるダイナミクスを論じるというもの(ああっ、こんな乱暴なまとめ方ですいません)。たとえば日本ファシズムの形成についてもそのような手法を駆使され多くの研究を出されていたが、近年は市民運動に関する研究に従事されており、この書籍はその研究の総まとめ(の一つ)。
本書は研究書なのだが、冒頭の東京オリンピックに関する記述から物語が始まり、ベ平連成立から解散に至る詳細な歴史記述へと続きまるで一つのルポルタージュのような作り。映画のように、広角レンズで描いた東京オリンピックの風景が、クローズアップしていき個別のベ平連史にフォーカスされ、そして再び広角レンズによってベ平連の終焉が描かれ、余韻を残したまま終わる・・・というような、かつての日本映画のような構成になっている。
サブタイトルになっている「身ぶりとしての政治」は、終章の末節、つまり本書をしめくくる最後の文章のしかも節タイトルまで登場しない。著者は「身ぶり」を
「単なる身のこなしという意味だけではなく、人々が他者とコミュニケートをとろうとする際の、発話から表情、そして身のこなしや振る舞いまでを含む幅広い意味をもつ」(p.279)
と示し、ベ平連の運動の中心人物達はこうした「身ぶり」による運動を指向していたとする。読者はここまで様々な事例を読み進めることを通してぼんやりと感じていたことが、最後に示されたサブタイトルによって明確に言語化され意識することができると思う。
個人的に面白いなと思った「身ぶり」の具体例は、第六章「フォークソングとハンパク −対抗文化運動としてのベ平連」。中でも、引用されている古川豪によるフォークソングとうたごえ運動のちがいについての発言がとても興味深い。
「フォークソングは、結構一人称なんですよね。(中略)それとリーダーがアコーディオンを引きながらその人のもとで歌うというよりは、個人の集まりが一つの歌になる。その辺の違いみたいなのがある」(p.188)
コロナ禍での社会(正確には2011以降の「絆」が何かと強調される社会)では、多様性がある個人の集まりによって社会が形成されていることが否定されてきた。主語がI(わたし)の集合体から、We(わたしたち)という一つの塊となり、I(わたし)の存在はWe(わたしたち)の中で「ないものになった」ように思う。このフォークを巡る話とも重なるように思うが、どうだろうか。そして、こうしたI(わたし)の違いを尊重するベ平連だからこそ、発展的に解散に至ったのだと思い至る。
平井先生からは、学問そのものよりも例えばマンガや映画であるとか(山上たつひこの素晴らしさを力説されたり、滑稽新聞をお借りしたり、原一男について教えてもらったのも先生でした)いろんなことを教わった。でもフォークの話はあまり聞いたことがなかった。師の背中は大きく、自分の不勉強を恥じるばかりだ。